冷凍・レトルト・包材で、食材をムダにしない。〜工夫で変わる、フードロスの現場〜
食材の廃棄を減らすため、いま飲食店や食品関連事業者の間では冷凍技術やレトルト食品、機能性包装資材への注目が高まっています。今回は現場で実際に工夫を重ねる店舗や企業の声をもとに、フードロス削減に役立つアイデアと取り組みをご紹介します。
フードロスが起こる現場では、何が起きている?
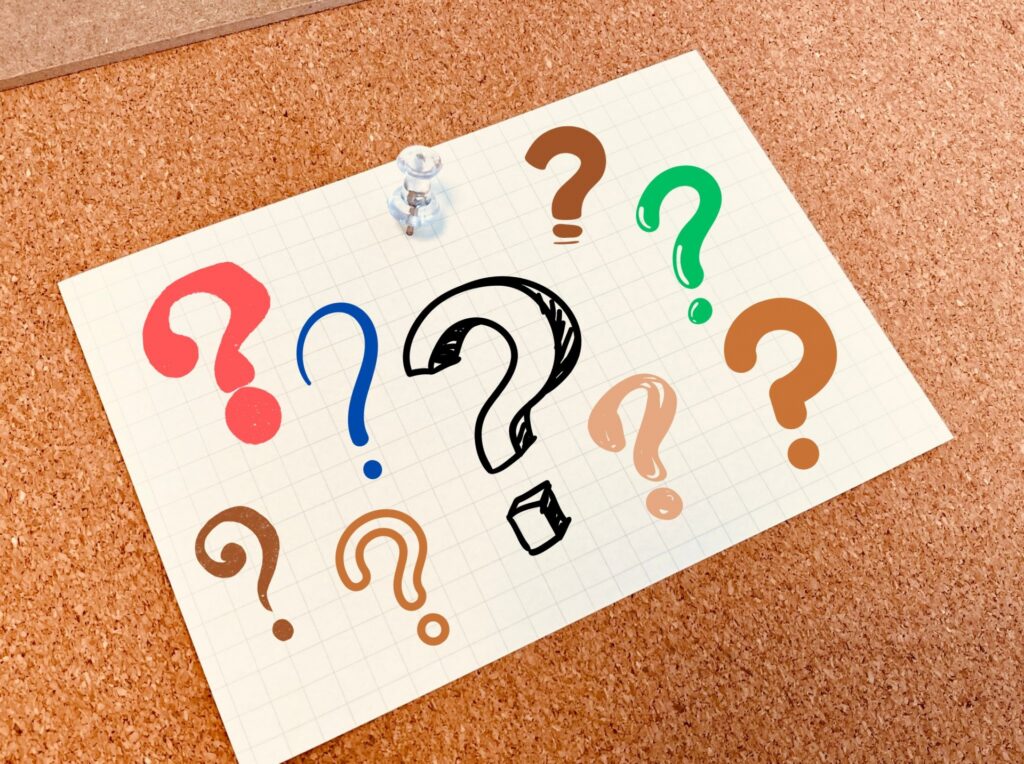
フードロスと聞くと、食べ残しや廃棄された食品をイメージする方が多いかもしれません。しかし、企業の現場ではもっと早い段階からロスが発生しています。特に小売店や飲食店、食品工場などでは、「まだ食べられる食品」が日々廃棄されているのが現実です。
最も多い要因の一つが「売れ残り」です。販売計画や需要予測が外れ、棚に商品が残ってしまうと、やがて賞味期限切れを迎えて廃棄されることになります。繁忙期や天候による営業など、予測困難な要素も多いため、完全なコントロールは難しいのが現状です。
次に多いのが「急なキャンセル・納品先の変更」です。特に外食チェーンやイベントなどでは、直前のキャンセルや仕込み済みの食材が行き場を失うケースも珍しくありません。このようなロスは、事前の連携や販売先の多様化で緩和できる場合もあります。
また、仕入れや調理の「予測ミス」もロスにつながります。需要を読み違えた仕入れによって在庫が過剰になると、使い切れずに廃棄されます。飲食店では、食材の使い回しやアレンジ力でカバーすることもありますが、制約もあるので限界があるのが現状です。
在庫や賞味期限の”見える化”やITを活用した在庫管理など、現場のサポート体制の見直しも大切になってきます。
フードロスは、ただ「もったいない」で終わる問題ではありません。仕入れコスト、処分費用、企業イメージへの影響など、経営に直結するリスクがあります。だからこそまずは、現場で何が起きているかを正確に把握し、対策を講じていくことが重要ではないでしょうか。
冷凍・レトルト・包材がフードロスを防ぐ

包装と保存技術で、フードロスを防ぐことはもちろん、ビジネスチャンスに変えることができます。日持ち=売れるチャンスを作ることができるのです。
食品業界では今、「フードロス削減」が社会的責任であると同時に、ビジネス価値の向上にも直結するテーマとなっています。特に注目されているのが、製造や包装の工夫によって「食品の日持ち」を延ばす取り組みです。日持ちの延長は、販売機会の拡大や在庫管理の柔軟性、廃棄コスト削減など、企業にとっても大きなメリットをもたらすのです。
冷凍・レトルト・包材別にどのようにフードロスを防ぐことができるのかをご紹介します。
①冷凍技術の進化…急速冷凍で品質をキープ
冷凍保存はすでに一般的な手法ですが、「急速冷凍」により、さらに品質を保った長期保存が可能となりました。急速冷凍は細胞破壊を防ぐことで、解凍後も味・食感が損なわれにくく、販売後の満足度も維持できます。製造段階で急速冷凍を行い、小分け包装しておけば、必要なタイミング。数量が供給できるため、在庫ロスのリスクを大幅に抑えることができるのです。
②小分け包装…使い切りやすく、無駄を減らす
製品を小分けにすることで、消費者が「必要な分だけ」を使える設計となり、使い残しによる廃棄を防ぐことが可能です。飲食店や小規模事業者などへの業務用展開でも利便性が高く、用途に応じた使い切りパッケージはフードロス削減に効果的です。
③レトルト加工…常温保存で販売・流通の自由度向上
レトルト加工することにより、冷蔵・冷凍設備なしで長期保存が可能となり、流通面の制約が軽減されます。賞味期限の長さが、販売機会の拡大につながり、備蓄用やギフト、海外輸出など新たな販路の開拓にも貢献します。
④包装資材の工夫…品質保持と利便性を両立
酸素・湿気などを遮断する機能性包装資材の活用は、食品の劣化を防ぎ、品質保持期間を延ばします。チャック付きやスタンド型など、利便性を高める仕様にすることで、使い残しの廃棄防止にもつながります。こうした包材の工夫が、消費者の「使い切りやすさ」へとつながり、最終的にはロスの削減に貢献するのです。
日持ちさせることは、フードロス削減にも繋がり、更に売れるチャンスを増やすことにも繋がります。
現場に聞いてみたフードロス削減アイデア

地域の飲食店や製造現場にフードロスの対策について伺いました。
飲食店では、食材を半調理して冷凍保存し、必要な分だけ使う工夫を実施しています。野菜は廃棄部分が出ないカット野菜を使用しているそうです。「少しの工夫で、無駄は減らせます」と教えてくださいました。
居酒屋の店主は「利益を出すためには廃棄を出さない。基本は”あるもので”やる」と教えてくださいました。仕入れのコントロールと柔軟なメニュー展開で、ロスを最小限に抑えています。
製造業者さんでは賞味期限が近い商品を自販機で半額で販売しているとのことでした。「お客様にも喜ばれ、廃棄も減らせます」と好評なようです。
お寿司屋さんでは、しゃりが余る課題に頭を悩まされています。ネタが余った場合は、煮付けや味噌汁の具材として再活用し、「少しでも無駄を減らす工夫をしています」とお話いただきました。
また、スーパーさんでは、「売れ残りそうな商品は段階的に値引きシールを貼って売り切る」取り組みを実施。それでも残れば廃棄となるため、「天候やチラシの影響を見て販売量を調整している。処理にもコストがかかるため、今後はさらに値引きを柔軟に検討したい」とのことでした。
製造業者さんで「まだ対策はしていないが、今後の課題」との声もありました。他店の工夫を学びたいと考えておられるそうです。
それぞれの現場で試行錯誤を重ねる姿から、フードロス削減の鍵は”身近な工夫”にあることが見えてきました。
インタビューにご協力くださった皆様、お忙しい中ありがとうございました。
まとめ
いかがでしたか?フードロスという言葉は何気なく耳にすると思います。消費者目線で捉えがちですが、製造業者や飲食店など様々な場面で対策できることが分かりました。企業も消費者もそれぞれできる対策をすることが大切ですね。
フードロス対策はもちろん、急速冷凍を使ってこんな商品を使いたい、保存したいなどお考えの方はスパックラボで一度機械を実際に目で見てみてください!

